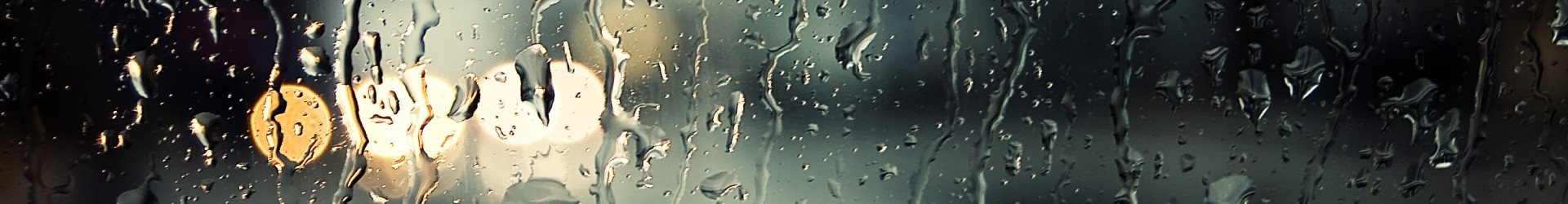かつて、病状がひどかった時、
言葉はいつも頼りないものに思えたし、
かといってこの指先が何かを掴むことはおろか、
触れることも覚束なかったから、
だから、僕は、
ただ、世界に、居たんだ。
たしかに世界はいつも、在った。
在ったが、それもまた、不安の種だった。
朝が来て、夜になり、また、朝が来る。
そんな野放図な繰り返しが、雑然としたものに感じられたのだ。
どうして、昨日も生きた今日を生きねばならないのか?
否応なく訪れて否応なく去っていく時とは、なんと無情で残酷か。
夢を見せて、夢を奪う、時間というものの意地悪な感じにつくづく嫌気が差していた。
静けさの中に、記憶を探す。
白紙の手帳を前にして、過去なのか未来なのかさえ分からない日付と言われる数字を眺めていた。
そこには、本当に、何の意味も見つからなかった。
いまは毎日が、リハビリだ。
そぐわない意識と行為。ぎこちない日々。
毎日がゆらめいて、そしてやっぱり、覚束ない。
唾棄すべきなのか抱きしめるべきなのか分からない「日常」というやつに、曖昧な泣き笑いを向ける。
僕の表情が、とっても、醜くゆがむけれど。
たとえどんなに忘れまいとしても、時間は記憶を変容させる。
だから今の僕は、正しいことなど何も知らないと言っても間違いじゃないかもしれないと思う。
幾多の、記憶の断片が蘇っては消えていくのを今も変わりなく眺めているだけだ。
扉が、焼け落ちた先の、闇へ。
うつ病の、「寂しい」はあらゆる「怒り」が変容したもののような気がする。
僕自身、怒りが、体の奥に残っているのを自覚している。
だから、たまに思う。
自分を許すために。
僕のことを「弱い」と蔑んだお前、覚えていろ、と。