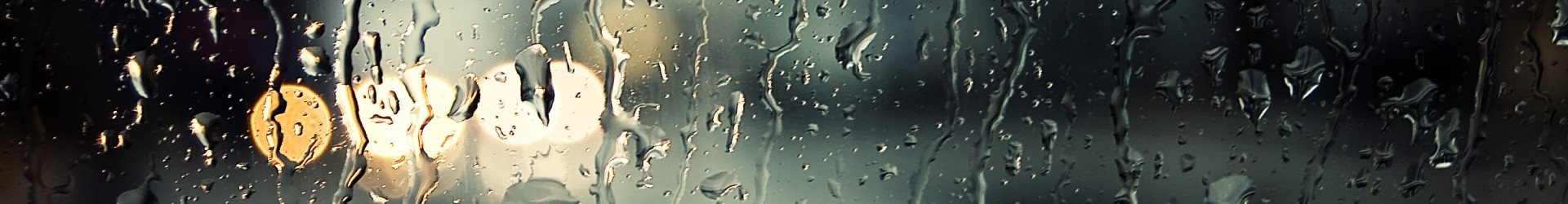石川淳(1899〜1987)は1935年、処女作「佳人」を発表し、1937年「普賢」により芥川賞を受けた。
さらに第二次世界大戦後(1945〜)も、1946年に「焼跡のイエス」1948年に「処女懐胎」1949年「最後の晩餐」などを発表し、太宰治、坂口安吾、織田作之助らと並び「無頼派」と称され、めざましい活動を展開した作家である。また、後期長編小説群と呼ばれる「至福千年」(1967年)「狂風記」(1980年)なども有名。安部公房か師事した人でもあり、安部公房の初期作品集『壁』に序文を寄せている。
最近、故あってキリストやイエスと名のつく積読本を漁っていて、ふと目に留まったのが「焼跡のイエス」である。(ずいぶん以前、購入した時に一度読んだきりだった文庫本の奥付けを見ると、平成八年に二十六刷とある。)
さて、この作品にイエスはいるか?
それが関心ごとだった。
描かれているのはどのようなイエスなのか。
読んだ。
この作品の中のイエスとは、闇市の中で、他者から奪ってでも自らは生きんとする、いわば生物の自然な欲望を明らさまに発露した少年のことだった。 石川淳は、聖なるイエスと賤なる浮浪児を同時に描くことで、賤の中に聖性を見出したのか。
それははっきりとは書かれていない。
「石川淳評論選」(ちくま文庫)中に、短編小説とは何かについて論じた部分がある。
「ドストエフスキーの小説についてよくいわれているように、途中で思いがけない新人物が出現するとか、突然主題が別の方向へ発展して行くとか、一見ふしぎなこれらの現象にこそちゃんと正当な理法がはたらいているので、およそ傑作と呼びうるほどものはみなこの筋道を踏んで来ている。」(略)「作品はつねに闇の戸口からはじまる。そしてその終わるところもまた闇の中でしかないので、一つの作品が出来上がったおかげで、ただちに未知の法則の一つが解明されるというような重宝な仕掛けにはなっていない。」(「短編小説の構成」)
我々が生きる「現実」とは何か。
「現実」とは我々人間の認識の場である。
別の言い方をすれば、認識の範疇である、ということだ。
現実世界を生きている、ということはそれがすなわち、事実を全て享受して生きているということではない。
人は全てを認識できないからだ。
人は認識できる範囲において認識し、そのなかかからさらに取捨選択を繰り返しながら判断の糧とし、その判断をもとに再構成した各々の「現実」を生きているのだ。
小説は「現実」の僕(しもべ)である必要はない。
事実は事実だが、その事実は不正確だ。
小説はむしろ、その事実の破れ目から覗く別の現実に支えられてある。
私が小説を読みたいと願うのは、現実にあきたらないからだ。
現実よりもっと訳のわからない感銘(のようなもの)に吹きまくられるような読書体験を求めているのだ、と、自ら気付くことができて良かったし、同時にまた、それが小説を書こうとする理由の一つだと言っておこう。
読後、私はSNSに読後感想を以下のように書いた。
石川淳「焼跡のイエス」読了。 「聖戦」だったはずの第二次大戦後の闇市と浮浪児と「ナザレのイエス」。聖と賤の転換、昇華、再生の予感が独特の文体で描かれる。 他の作品も読みたい。