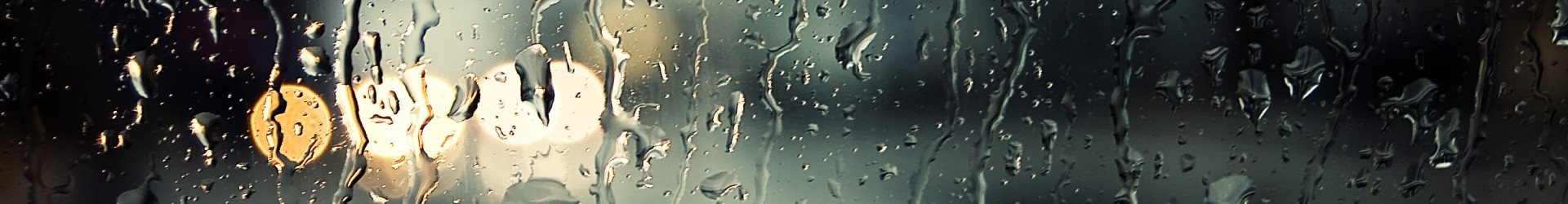大江健三郎が石川淳を愛読していたとは知らなかったな。
石川淳にとっての森鴎外みたいなものかしらん。
以下、大江の文章を引いてみる。
|
「戦後、僕は敗戦後の現実を体験し、かつ、いわゆる戦後民主主義に、もっともはっきりひらかれた行先を見る、ということをつうじて、青春にむかいつつありました。
そして、その僕における、最初の、かつ、最も鋭く自分をとらえる、真の「戦後文学」が、石川淳の作品であったのです。
僕は、同年輩の友人たちと、いかにしばしば、石川淳の世界について語りあったことでしょう。
奇妙なことに、僕らは、石川淳が、どういう閲歴を過去につんできた作家であるかを、まったく知りませんでした。
作家の年齢すらも、知ることがなかったのです。
しかも、僕らは石川淳の、ありとあらゆる小説をさがしもとめてきては、酔っぱらったようになって、それに読みふけり、かつそれを礼讃する言葉を発しあったのです。
僕らは、おなじように熱狂する作家として、というより作品として、敗戦まえに出版されたカフカ『審判』を持っていました。
そしてそのカフカについても、ほとんどなにひとつ知らなかったのでした。
僕は、純粋に、文学の領域に没頭することにおいて、少年がみずから熱狂的に選びとる道筋には、まともな重みがあると考えています。
かれは、その生涯を、ついにその道筋にたくすことになるのではないかという、恐ろしい予感とともに、鋭敏な嗅覚によって、かれ自身の唯一の道筋を選ぶのです。
熱狂のうちに、選び取り、静かに醒めて、なお選びつづけるのです。」
(『新潮日本文学33 石川淳集』 から、「解説――若い世代のための架空講演」)
|
 石川淳
石川淳
大江にとって石川淳はカフカと並んで重要な作家だったのだね。
そして、「純粋に、文学の領域に没頭することにおいて、少年がみずから熱狂的に選びとる道筋には、まともな重みがあると考えています。」という一言を読む時、文学少年・大江健三郎がやがては世界的作家・大江健三郎になっていったことを思えば、石川淳がもたらし、大江健三郎が受け取った「まともな重み」がいかに意味の深いものであったかを感じずにはいられないな。
加藤周一「日本文学史序説」