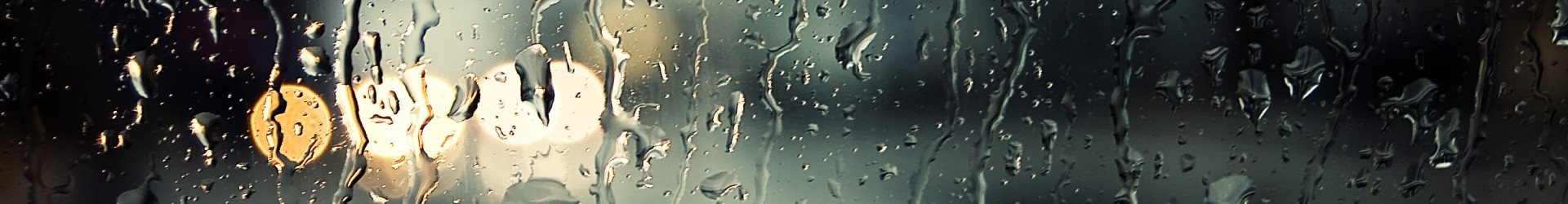大江健三郎が亡くなって、「読書」といえば大江健三郎の本ばかり読み、考えるようになってしまった。
より実感的な言い方で言えば、その作家の一生を通して書かれ続けた作品の熱量と物理的な量を前に茫然として途方に暮れているといったところである。
蓮實重彦は「読書」について言っている。
実際、「読書」とはあくまで変化にむけてのあられもない秘儀にほかならず、読みつつある文章の著者の名前や題名を思わず他人の目から隠さずにはいられない淫靡さを示唆することのない読書など、いくら読もうと人は変化したりはしない。(蓮實重彦『随想』2010年)
とりあえず何でもよかったのだがこの稀代の作家を読み返そうかという気になって、「人生の親戚」(1989)を読み返した。
「個人的な体験」とどちらを読むか迷ったのだが、自分自身の身体障害のことを小説化しようとしている現在、避けたいような気がしたのだった。
加えて、三島由紀夫が大江の「個人的な体験」の末尾は不要だ、これは「主人持ちの文学だ」と批判した文章を何かで読んだことをふと思い出しもした。(その三島の文章はWikipediaによれば、1964年9月の「週間読書人」に掲載されたということで、その文章を探してみたが、三島の批評とそれへの大江の応答が見当たらない。いつどこで目にしたのだろう。)「主人持ちの文学」とは、通俗的な文学という意味だろう。
ツイッターなどをつらつら眺めていると、大江への追悼の呟きも多いがそのなか目に留まった「左翼で俗物」というのがあって、そのすぐ後に「本物の才能」とも書いている。小説あるいは小説家にとって「俗物」、「凡庸」、「通俗」、とは。
それで思い出したのがこれ。ナボコフ『ロシア文学講義』の中の一節。
俗物は成熟した大人であって、その関心の内容は物質的かつ常識的であり、その精神状態は彼または彼女の仲間や時代のありふれた思想と月並みな理想にかたちづくられている。(中略)「ブルジョア」という言葉を、マルクスではなくフローベールの用例に従って私は用いる。
フローベールの意味での「ブルジョア」は一つの精神状態であって、財布の状態ではない。
ブルジョアは気取った俗物であり、威厳ある下司である。
順応しよう、帰属しよう、参加しようという衝動にたえず駆り立てられている俗物は、二つの渇望のあいだで引き裂かれている。
一つは、みんなのするようにしたい、何百万もの人びとがあの品物を褒め、この品物を使っているから、自分も同じものを褒めたり使ったりしたい、という渇望である。
もう一つは排他的な場、何かの組織や、クラブ、ホテルなどの常連、あるいは豪華客船の社交場(白い制服を着た船長や、すばらしい食事)に所属し、一流会社の社長やヨーロッパ の伯爵が隣に座っているのを見て喜びたい、という渇望である。
いずれにせよ、「どこか」「何か」への帰属願望のことなのか。
ただし、「帰属願望」と言っても一筋縄ではいかないのが小説家または読書家の面白い(面倒臭い)ところで。
文学がその自意識に目覚め、文学ならざるものとの違いをきわだたせることにその主要な目標を設定していらい、過去一世紀に及ぶ文学の歴史は、同じであることをめぐるごく曖昧な申し合わせの上に、かろうじて自分自身を支えてきたといってよい。
最初にあったのは、同じでありたくないという意志であり、その意志の実現として諸々の作品が書かれてきたのだが、より正確にいうなら、こうした文学的な自意識の働きは、それじたいとして故のない妄執をあたりに波及させてきたわけだ。
実際、同じではありたくないという意志が等しく共有される場として文学が機能していたという事実は、何とも奇妙な自家撞着だというべきだろう。
作家たちは、また読者たちも、自分が他と違ったものでありたいという同じ意志を、何の矛盾もなく文学の価値だと信じていたからである。
つまり、近代と呼ばれる時代の文学は、文学が一般化されてはならず、あくまで特殊な振舞いとして実践されねばならないという一般化されて欲望が、みずからの矛盾には気づくまいと躍起になって演じたてられた悲喜劇にすぎず、それこそ文学の自意識なるものの実体にほかならない。
特殊でありたいといういささかも特殊ではない一般的な意志、あるいは違ったものでなければならぬという同じ一つの強迫観念が、文学をどれほど凡庸化してきたかは誰もが知っている歴史的な現実である。
文学の近代的な自意識なるものによって捏造された個性神話というものが、とどのつまりは文学の非個性化に貢献してしまったという歩みそのものが、そのまま過去百年の文学の不幸な歴史にほかならない。(蓮實重彦『小説から遠く離れて』1988年)
大江健三郎が亡くなって、大江健三郎を改めて読み始めると、当の小説家が生きて新しい作品を世に出してくれていた頃には感じなかった別の感慨もまた浮かぶ。
もう新しい作品は出ないのだ、もう、彼の作品は「更新」されないのだという感覚だ。
今後、その作家の作品の「読み方」に新たな何かが加わることはないのか、という絶望感とともに、私たちは残された作品を「鑑賞」するだけなのだろうか、という戸惑い。
一人の作家が作り上げた物語の奥底に秘められた「声」に耳をすまそうとすることなく、ただ淡々と、静かに、博物館のケースの中の逸品を、手に取ることもせず「鑑賞」することだけが残された読みの可能性であるなら、私は今後、誰の作品も読みはしない。
私は、私の前に突如現れた(ように見える)一人の作家の作品群を前に茫然としながら、私はまだ、ほんの少ししかこの人について「知らない」のだということを確認するばかりだ。
だが、知っているとはどういうことなのか。
ほとんどの場合、知っているとは、みずから説話論的な磁場に身を置き、そこで一つの物語を語ってみせる能力の同義語だと思われている。
フローベールとは、十九世紀フランスの小説家で、『感情教育』などの客観的な長篇小説を書いた、というのがそうした物語である。青年時代に神経症の発作に見舞われていらい、世間との交渉を絶ち、ノルマンディーの田舎に閉じこもって、文章の彫琢に没頭した、というのも物語である。また、その他いろいろあるだろう。
そんな物語の一つをつぶやくことができるとき、人は、そこで主題になっているものを知っていると思う。知は、物語によって顕在化し、また物語は知によって保証されもするわけだ。
なにひとつ物語を語りええないものを前にして、人はそれを知らないという。
だから、フローベールが未刊のままの草稿として残した倒錯的な辞典の題名をかかげてみても、知と物語との相互保証を導きだすことにしかならないだろう。
ところで、フローベルが十九世紀の半ばに構想を得た辞典は、まさに、こうした知と物語との補完的な関係を断ち切ることにあったのだ。
実際、誰もがフローベールを知っている。
そして、知っているという事実をたがいに確認しあうために、人は、フローベールをめぐって誰もが知っている物語を語りあう。
その物語の中で、最も多くの人に知られているものこそ、フローベールが執筆を企てた辞典の項目たる資格を持つものである。
誰にでも妥当性を持つことで、誰もがそれを口にするのが自然だと思われる物語。
それが、知の広汎な共有を保証し、その保証が同じ物語を反復させる。
かくして知は、説話論的な装置の内部に閉じこもる。
まるで物語の外には知など存在しないかのように、装置は、知を潤滑油として無限に機能しつづける。するとどういうことになるか。
結果は目にみえている。
人は、知っていることについてしか語らなくなるだろう。
たまたま未知のものが主題となっているかにみえる物語においてさえ、人は、それを物語ることで、既知であるかの錯覚と戯れる。
あるは逆に、既知であるはずのものを、あたかも未知であるかのようなものにする。
だから、物語は永遠に不滅なのだ。
ところで、この物語の無限反復の中に辞典の題名を導入するとどうなるか。
それはギュスターヴ・フローベールの未完の草稿だと口にするだけで、この辞典が説話論的な磁場の中へ姿を消してしまうのは明らかだろう。
あとはすべてが円滑に進行する。
その倒錯的な辞典の倒錯性そのものに出会うことなく、誰もが物語を納得してしまうのだ。
だが、フローベールとしては、みずからを無謀な編纂者に仕立てあげることで、この寛大な納得を、物語の模倣を介して宙に吊ることを目ざしていたわけだ。
というよりむしろ、説話論的な磁場の保護から出て、誰もがごく自然に口にする物語を、その説話論的な構造にそって崩壊させるというのが、彼の倒錯的な戦略であったはずだ。
物語に反対の物語を対置させることではなく、物語そのものにもっとも近づいて、自分自身を物語になぞらえさえしながら、物語的な欲望を意気阻喪させること。
つまり、失望の生産とは、知と物語との補完的な関係をくつがえし、知るとは、そのつど物語を失うことにほかならなぬのだと、実践によって体得すること。
事実、具体的に何ものかと遭遇するとき、人は、説話論的な磁場を思わず見失うほかはないだろう。
つまり、なにも語れなくなってしまうという状態に置かれたとき、はじめて人は何ごとかを知ることになるのだ。
実際、知るとは、説話論的な分節能力を放棄せざるをえない残酷な体験なのであり、寛大な納得の仕草によってまわりの者たちと同調することではない。
何ものかを知るとき、人はそのつど物語を喪失する。
これは、誰もが体験的に知っている失語体験である。
言葉が欠けてしまうのではなく、あたりにいっせいにたち騒ぐ言葉が物語的な秩序におさまりがつかなくなる過剰な失語体験。
知るとは、知識という説話論的な磁場にうがたれた欠落を埋めることで、ほどよい均衡におさまる物語によって保証される体験ではない。
知るとは、あくまで過剰なものとの唐突な出会いであり、自分自身のうちに生起する統御しがたりもの同士の戯れに、進んで身をゆだねることである。
陥没点を充塡して得られる平均値の共有ではなく、ときならぬ隆起を前に、存在そのものが途方に暮れることなのだ。
この過剰なるものの理不尽な隆起現象だけが生を豊かなものにし、これを変容せしめる力を持つ。
そしてその変容は、物語が消滅した地点にのみ生きられるもののはずである。(蓮實重彦『物語批判序説』1985年)
ぼくは、自分を咬んだり、刺したりするような本だけを、読むべきではないかと思っている。
もし、ぼくらの読む本が、頭をガツンと一撃してぼくらを目覚めさせてくれないなら、いったい何のためにぼくらは本を読むのか?
きみが言うように、ぼくらを幸福にするためか?
やれやれ、本なんかなくたってぼくらは同じように幸福でいられるだろうし、ぼくらを幸福にするような本なら、必要とあれば自分で書けるだろう。
いいかい、必要な本とは、ぼくらをこのうえなく苦しめ痛めつける不幸のように、自分よりも愛していた人の死のように、すべての人から引き離されて森の中に追放されたときのように、自殺のように、ぼくらに作用する本のことだ。
本とは、ぼくらの内の氷結した海を砕く斧でなければならない。(カフカ 親友オスカー・ポラックへの手紙 1904年1月27日)