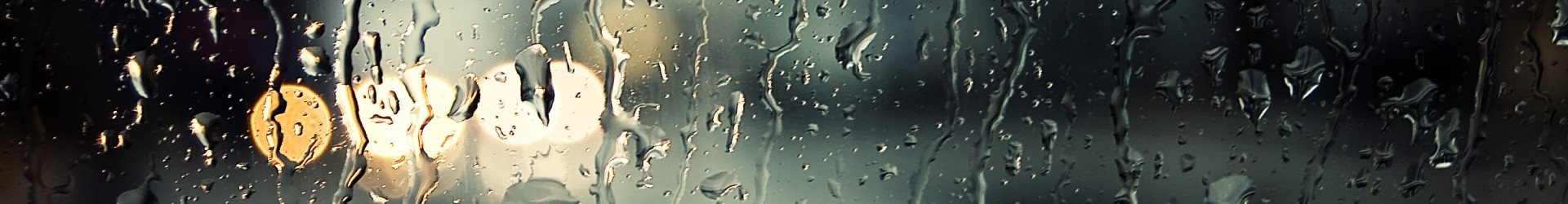この記事は多分、一冊の本についてその感想を書いたり、況してや書評を書いたりするような意味での「レヴュー」にはならないと思う。
私は、最近、石川淳の「焼跡のイエス」「処女懐胎」などの短編をいくつか読んだ。
(なぜそれらを読んだのかと言うその理由らしきものは前回の記事に書いた。)
石川淳の文章は私を捉えた。
その理由は今ここには書かないが、その書かれた「文章」の姿に惹かれるものがあったことは確かだ。
石川の創作以外にも何か読みたいと本棚を漁って、引っ張り出したのが、ちくま文庫の「石川淳評論選 石川淳コレクション3」だった。その中に「敗荷落日」がおさめられているのを改めて見出した。
思い返せば、むしろ、この本を買った当時、「敗荷落日」が収められてあるからこそ当該書籍を買ったはずなのだ。十代の頃の私にとって石川淳といえば、「敗荷落日」の人だった。
少し時間を遡るが、かつて、太宰治を読んでいた時期、私は坂口安吾、織田作之助とともに、石川淳の名を知った。坂口安吾は「堕落論」「教祖の文学」「白痴」「不良少年とキリスト」「桜の森の満開の下」など読み、織田作之助は「夫婦善哉」「アド・バルーン」「世相」「競馬」であった。そんな時、ふと、石川淳の本を何か、なんでもいい読んでみようと思い立ち、当時住んでいた横浜市の図書館に向かったのである。
季節は秋の終わり頃だったと思う。その夕方だった。図書館の閉館時間にはまだ余裕があったが、夏が過ぎて日が短くなりつつあって肌寒さも加わるため、自転車を漕ぐ足は自然、急いた。
図書館の隅の文庫本の棚に石川淳の本がいくつか並んでいたその中の一冊を抜き取り読んだものが、永井荷風について記した一文「敗荷落日」だったと記憶する。文庫本の棚は図書館の中でも奥まった窓際の一角にあってその近くには机も椅子もなかったので、しゃがんで棚を覗き込んだ後選び取った一冊を読むため、辺りに他人の気配がなかったこともあり、その場に座り込んで読み始めた。
読むため座り込んだその場所は西日が窓から射し、僕はその差し込む日に照らされる一角に座り込んでいるような記憶があるのだが、どうもそれは錯覚、というか記憶違いのような気がする。
「敗荷落日」は、その容赦ない苛烈さゆえに、読後感も強烈だった。
だがその文章が容赦なく苛烈でありながらどこか悲しげなのが気になり、ずいぶん後になって評論選を買ったのだ。
いま、手元にある「敗荷落日」の中で、石川淳はこう書いている。
一箇の老人が死んだ。通念上の詩人らしくもなく、小説家らしくもなく、一般に芸術的らしいと錯覚されるようなすべての雰囲気を絶ちきったところに、老人はただひとり、身近に書きちらしの反故もとどめず、そういっても貯金通帳をこの世の一大事とにぎりしめて、深夜の古畳の上に血を吐いて死んでいたという。このことはとくに奇とするにたりない。小金をためこんだ陋巷の乞食坊主の野たれじにならば、江戸の随筆なんぞにもその例を見るだろう。しかし、これがただの乞食坊主ではなくて、かくれもない詩文の家として、名あり財あり、はなはだ芸術的らしい錯覚の雲につつまれて来たところの、明治このかたの荷風散人の最期とすれば、その文学上の意味はどういうことになるか。
おもえば、葛飾土産までの荷風散人だった。戦後はただこの一篇、さすがに風雅なお亡びず、高興もっともよろこぶべし。しかし、それ以後は……何といおう、どうもいけない。荷風の生活の実情については、わたしはうわさばなしのほかはなにも知らないが、その書くものはときに目にふれる。いや、そのまれに書くところの文章はわたしの目をそむけさせた。小説と称する愚劣な断片、座談速記なんぞにあらわれる無意味な饒舌、すべて読むに堪えぬもの、聞くに値しないものであった。わずかに日記の文があって、いささか見るべしとしても、年ふれば所詮これまた強弩の末のみ。書くものがダメ。文章の家にとって、うごきのとれぬキメ手である。どうしてこうなのか。荷風さんほどのひとが、いかに老いたとはいえ、まだ八十歳にも手のとどかぬうちに、どうすればこうまで力おとろえたのか。わたしは年少のむかし好んで荷風文学を読んだおぼえがあるので、その晩年の衰退をののしるにしのびない。すくなくとも、詩人の死の直後にそのキズをとがめることはわたしの趣味ではない。それにも係らず、わたしの口ぶりはおのずから苛烈のほうにかたむく。というのは、晩年の荷風に於て、わたしの目を打つものは、肉体の衰弱ではなく、精神の脱落だからである。老荷風は曠野の哲人のように脈絡の無いことばを発したのではなかった。言行に脈絡があることはある。ただ、そのことがじつに小市民の痴愚であった。(中略) むかし、荷風散人が妾宅に配置した孤独はまさにそこから運動をおこすべき性質のものであった。これを芸術家の孤独という。はるかに年をへて、とうに運動がおわったあとに、市川の僑居にのこった老人のひとりぐらしには、芸術的な意味はなにも無い。したがって、その最期にはなにも悲劇的な事件は無い。今日なおわたしの目中にあるのは、かつての妾宅、日和下駄、下谷叢話、葛飾土産なんぞに於ける荷風散人の運動である。日はすでに落ちた。もはや太陽のエネルギーと縁が切れたところの一箇の怠惰な老人の末路のごときには、わたしは一灯をささげるゆかりも無い。
評論家の川本三郎は「荷風好日」の「あとがき」の中で、次のように書いている。
「荷風は戦後を余命と見,緩慢なる死の道を生きたのだと思う」と。
そして度重なる空襲などの戦争体験、それらに対する恐怖心が根底にあったのだと。だから、「荷風が戦後、急激に創作意欲をなくしていった一因には、この『恐怖症』があるように思えてならない」(「空襲による『恐怖症』」)だから、「石川淳の批判は、その後遺症の重大さを理解していない不親切なものだったとおもわざるを得ない」(「あとがき」)
石川淳の「敗荷落日」が荷風の「後遺症の重大さ」を「理解していない不親切なもの」かどうか、私にはわからない。
しかし、石川淳の「もはや太陽のエネルギーと縁が切れたところの、一箇の怠惰な老人の末路のごときには、わたしは一灯をささげるゆかりも無い」(「敗荷落日」)という、斬って捨てるような苛烈な書きぶりはどういうことだろう、という疑問が私にはある。
私が気になる点がもう一つある。
それは、「断腸亭日乗」の中に見られるとある人物についてだ。
よく知られているように、永井荷風はその死に近い頃まで「断腸亭日乗」という日記をつけていた。
その日記の中に「小林修」という人物が現れる。
私は荷風と小林修との交流が気になる。
小林青年は昭和23年頃より荷風の家屋の購入などを手伝い荷風のもとをたびたび訪れたとある。
『日乗』の4月28日にも「小林来る」という文言がある。
「荷風晩年の『日乗』に繰返される『小林来話』について川本は以下のように書いている。
「晩年の『日乗』に繰返される『小林来話』の意味は『正午浅草』よりむしろ重い。こういう青年と親交を保ち,死の前日にまで『小林来る』と書くことを忘れなかった荷風の最後の日々は幸福だったのではないだろうか」(「荷風と戦後」)
石川淳の言うように、作家永井荷風が「一箇の怠惰な老人」としてその人生を了ったとしても、その死の前日まで市井の人との交流を記した荷風の末路に一灯を捧げたいと、私は思うのだが。